【特定社労士試験】過去問の模範解答に関する「事実」と「評価」に関する疑問【紛争解決手続代理業務試験】
過去問の模範解答に関する疑問
読者様からのご質問
読者様からのご質問
志田先生のテキストでは、 " 第1問
小問②・③ には事実を記載し、 小問④ に評価を記載する"、とありますが、市販の模範解答を見ると、小問②・③に評価にあたる内容が書かれているものがあります。
どのように対応したら良いのか分からず混乱しています。
面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ の読者様から、上記のようなご質問を複数頂きました。
まずは結論から書かせて頂きます。
結論
- 実際の試験では、" 第1問 小問②・③ には事実を記載し、 小問④ に評価を記載" してください。
- 過去問の 第1問 小問②・③ 模範解答において、評価が含まれていると考えられる場合、ご自身で ”事実” と ”評価” に分けて解答を利用しましょう。
簡単な具体例
一度の軽微な入力ミスで会社に実損害を与えていない労働者Dを、会社がそのミスのみを理由に解雇したことは、処分として重すぎるため、解雇権の濫用にあたると考えられること。
上記の文章は、 ”事実” と ”評価” が混在しているので、このような模範解答が小問②・③にあった場合、ご自身で ”事実” と ”評価” に分けて解答を利用しましょう。
【事実】
- 労働者Dは、一度の軽微な入力ミスをしたこと。
- そのミスは、会社に実損害を与えなかったこと。
※ “労働者Dは、一度の軽微な入力ミスを犯したが、そのミスは、会社に実損害を与えなかったこと。" といった形でも問題ありません。
【評価】
- 上記のミスのみを理由とした解雇は、処分として重すぎる(著しく均衡を欠く)。
- したがって、この解雇は解雇権の濫用にあたる。
ポイント
小問②・③に ”評価” が含まれている場合、そのまま解答欄に記載する文章だとは考えずに、小問④へと繋がる、 ”思考プロセスの解説” がなされているという形で利用するようにしましょう。
事実 と 評価 を分けなければいけない理由は?
”事実” と ”評価” に分けなければいけない、というのは法律の条文に記載されている訳ではありません。
面白いほどよくわかる!特定社労士試験 では、あっせんも民事訴訟と同じように ”弁論” によって権利の主張を行っていくという解説をしました。
この ”弁論” を行う上で、もし、”評価” だけで ”弁論” を行うと、ただの言い合いになるだけで、話が進みません。下記の具体例で確認してみましょう。
【悪い具体例】評価だけで話す
あなた:「この解雇は無効だ!」(←あなたの評価)
相手:「いや、有効だ!」(←相手の評価)
これでは単なる主張の応酬であり、議論は進展しません。つまり、ただの言い合いです。
【良い具体例】事実から話す
あなた:「彼は、一度の軽微な入力ミスだけで解雇された。これが事実です。」
こう言われれば、相手は初めて具体的な反論ができます。「いや、そのミスは軽くなかった」とか「ミスは一度だけではなかった」というように、議論の的(まと)がはっきりします。
つまり、”弁論” という議論を行うためには、前提として ”事実” と ”評価” に分けて考える必要がある、ということです。これを法律的な表現で表すと、
「事実と評価の分離」という言葉を直接書いた法律の条文はない。しかし、この原則は、民事訴訟の基本理念である「弁論主義」から必然的に導かれる。
ということになります。
このような模範解答が生まれてしまった背景
さて、実際の採点基準は公表されていませんので、ここからは推測です。もし上記のように評価を含んだ解答を実際の試験で記述した場合、どのような扱いになるのか考えてみましょう。
小問②・③に ”評価” を記載してしまうとどうなる?
- 評価が書かれていたからといって、小問②・③の点数が即座に0点になる訳ではない。
- 記述式という試験の性質上、小問②・③に ”評価” が書かれている場合、減点になる可能性が高い。
つまり、”評価” を書いてしまっても減点される可能性はありますが、それを以って即座に合格点に届かなくなるという訳ではない、ということです。
特定社労士試験(紛争解決手続代理業務試験)は、受験者数が多くないため、出回っている情報が少ない試験です。特に、試験が始まった当初は、試験の形式も定まっておらず、 ”なんとなく、こんな感じのことを書いたら合格できた” という伝聞が、試験対策となっているような状況でした。
少なからず、模範解答もそのような影響を受けているものだと思われます。
模範解答によっては、ミスがあっても過去に掲載した解答は変更せずにそのまま掲載しているというものもあります。
また、昔の古い試験では小問②・③に ”評価” が含まれてしまっているけれど、近年の試験では、しっかりと ”事実” を掲載している、という模範解答もあります。
逆に、試験の形式や採点基準が明らかになってきた現在も、昔のまま、小問②・③に ”評価” が含まれてしまっている模範解答もあります。
私はそれらの著者ではないので想像することしかできませんが、模範解答によっては、小問②・③に事実のみを掲載すると、受験生に ”思考プロセス” が伝わりにくいと考えて、敢えて ”評価” を掲載しているものもあるようです。
ただ、結局大切なのは ”法的判断のプロセス” です。小問②・③に ”評価” を書けてしまうということは、頭の中では ”法的判断のプロセス” を辿れている可能性が高く、そのような解答は、減点はあるにせよ合格点には届く可能性も高いと思われます。
本来この試験は、研修の習得状況を確認するための ”確認試験” という位置付けの試験です。近年の合格率を見ると、そんな風には思えなくなってきていますが…。こういった性質が影響してか、 ”法的判断のプロセス” がどのような形になっているのか、解答全体の流れをみて得点の調整も行われているように見受けられます。
細かな点を挙げれば他にも考察すべき点はありますが、大筋としては、以上のような背景が考えられます。
これは私の意見になりますが、受験生側が学習をする際に混乱してしまう背景には、問題には数学のように完全に決まった解答がある、という思い込みが根本にあるためだとも考えています。
試験なので、ある程度の正答はありますが、民事訴訟がベースになっているので、絶対に100%これだ!という答えがある訳でもありません。どのような解答を記述するにしても、一貫した ”法的判断のプロセス” を示すことができれば、合格に近づくことができます。数学のように唯一絶対の正解を求めるのではなく、柔軟な思考で解答を組み立てる力が試されている、と考えると良いでしょう。
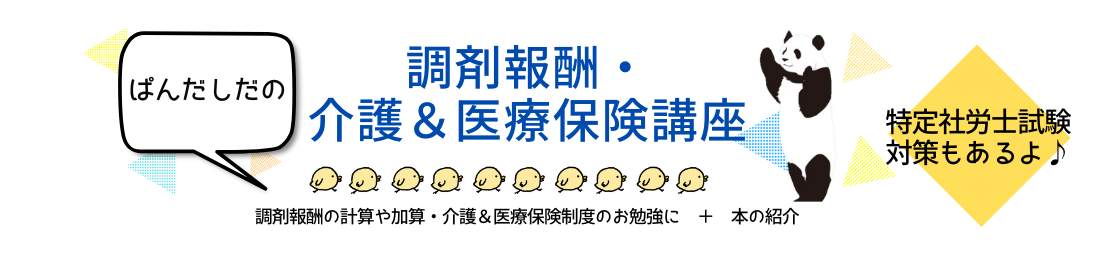





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません